 まんまるプップ
まんまるプップカリカリトロトロのたこ焼き!!


たこ焼き研究に余念がない小生。腕には多少の覚えがある。各所のタコパで無双し、羨望の眼差しを一身に受けてきた。
関西人を唸らせたこともある。(関西人はタコ焼きを外で買うので、意外に自分では作れないらしい。不戦勝)
ついに辿り着いた究極のひと玉!!
粉物がトロトロに仕上がる「じん粉」を使い、ガツンと旨くてハイカロリーなラードを使うレシピ。
また、焼き上がり直前でサラダ油を垂らすことで、たこ焼きが油を吸ってパンパンまんまるになり、揚げたこ焼きの要領で表面がガリガリザクザクに。
これは本当にヤバい。背徳の蜜の味である。
表面をなぞるとガリガリ音がし、割るとトロトロの生地🔥
皆様にも是非味わっていただきたく、ここにレシピを書き記す。ハイカロリーの背徳感と引き換えに、目ん玉が飛び出るほど旨いたこ焼きができるでしょう…
材料
まずは材料から。基本のたこ焼きレシピに「じん粉」、「ラード」を追加する。
「じん粉」は「浮き粉」とも呼び、小麦粉のデンプンを精製した粉である。(片栗粉の小麦バージョン)
スーパーであまり見かけないので、明石焼きの材料を扱っているお店やオンラインショップで入手。
材料(生地)
薄力粉:じん粉の比率は3:1〜2:1程度くらいが良い。1:1になると生地がかなり柔らかく、明石焼きに近くなる。
薄力粉の代わりに市販のたこ焼き粉を使う場合、じん粉を合わせて規定の量になるように調整する。
- 薄力粉 150g
- じん粉 50g
- だし 600g
- 卵 3個
材料(具材など)
サラダ油の代わりにラードを使用。ガツンと旨くてカリッと仕上がる。
- ぶつ切りタコ 150g
- ラード 適量
- ねぎ お好み
- 紅生姜 お好み。入れると銀だこっぽくなる
- 天かす お好み。カッパえびせんでも意外といける
調味料
調味料はお好みで
- ソース
- マヨネーズ
- 鰹節
- 青のり
脂っこいので、出汁でさっぱりいただくのもかなりオススメ
- 白だし
- 大根おろし
道具
究極の1玉のために、道具にもかなりこだわった。
鋳物のたこ焼き器
思い切って買った鋳物のたこ焼き器。ガス火と蓄熱性のおかげで、ホットプレートとは比べ物にならない火力が出せた。簡単にレビュー↓
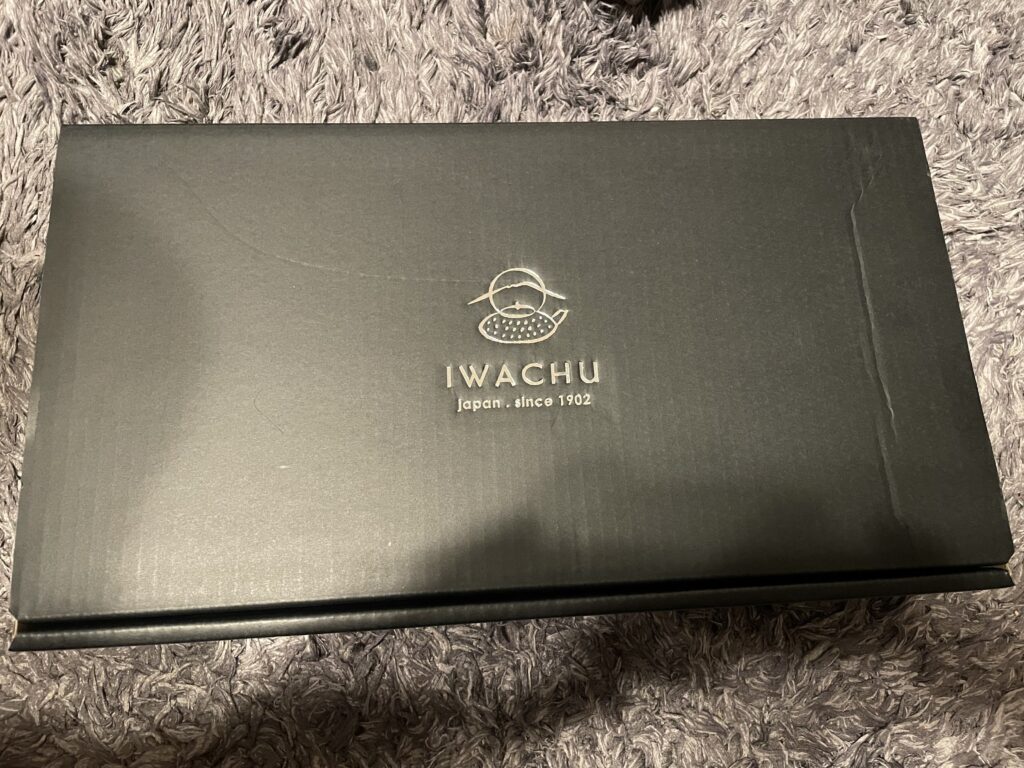
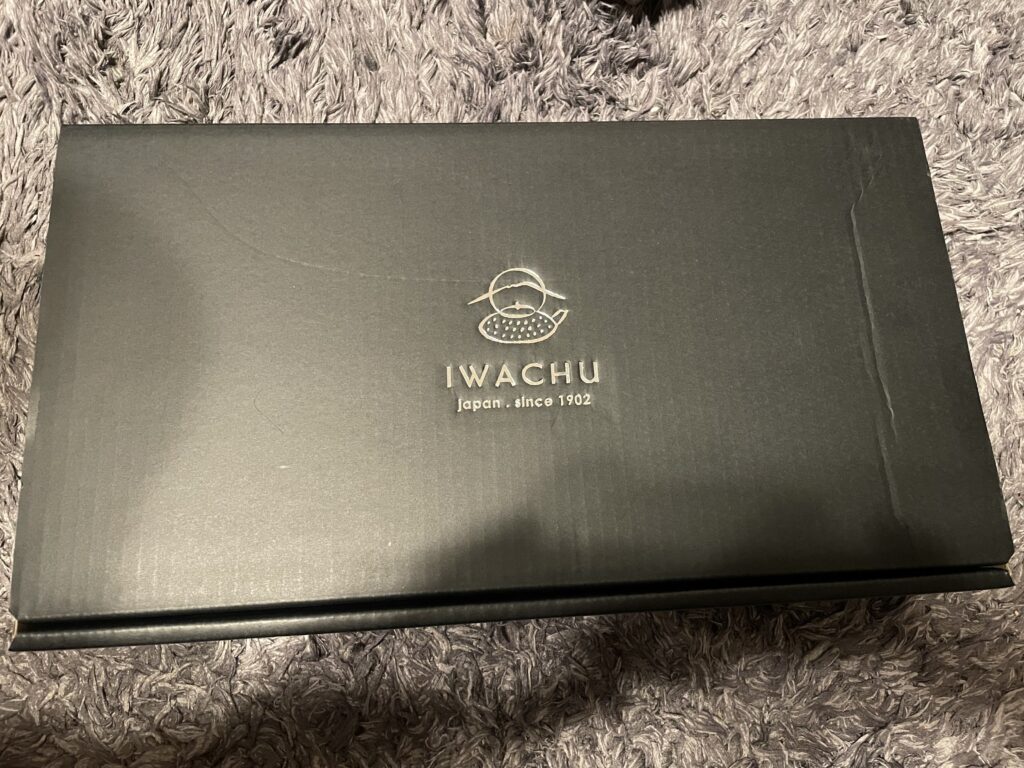


金属ピック
鋳物用に金属ピックも用意。これでガシガシ焼ける。(テフロン加工のホットプレートに使うと傷つけちゃうので注意!)
作り方


基本的な作り方は普通のたこ焼きと同じ!じん粉入りで生地が柔らかいので丁寧に作業する。
好きな配合で生地を作る


キッチンペーパーに脂を吸わせて、全部の穴に満遍なく塗る


一気に生地を注いてから具材を入れると、浮いてしまって綺麗に中に収まりにくい…
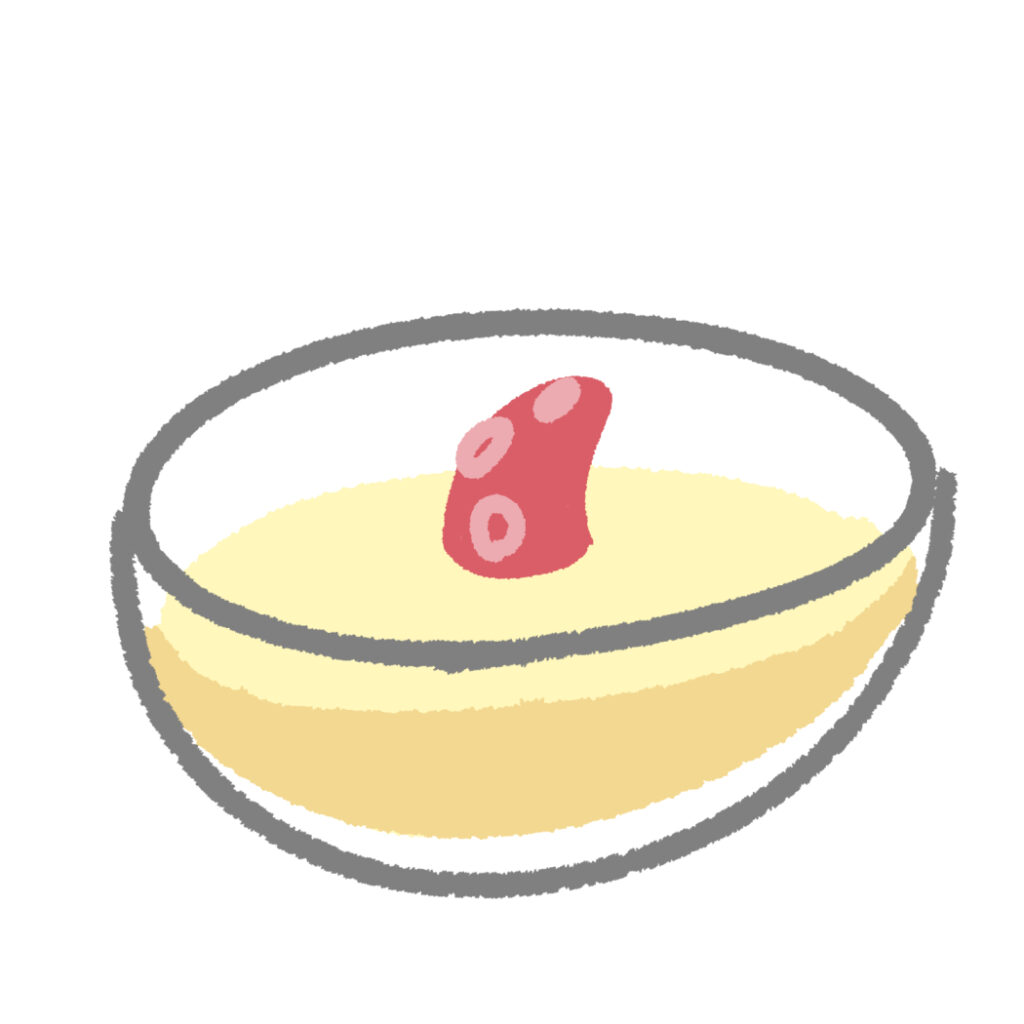
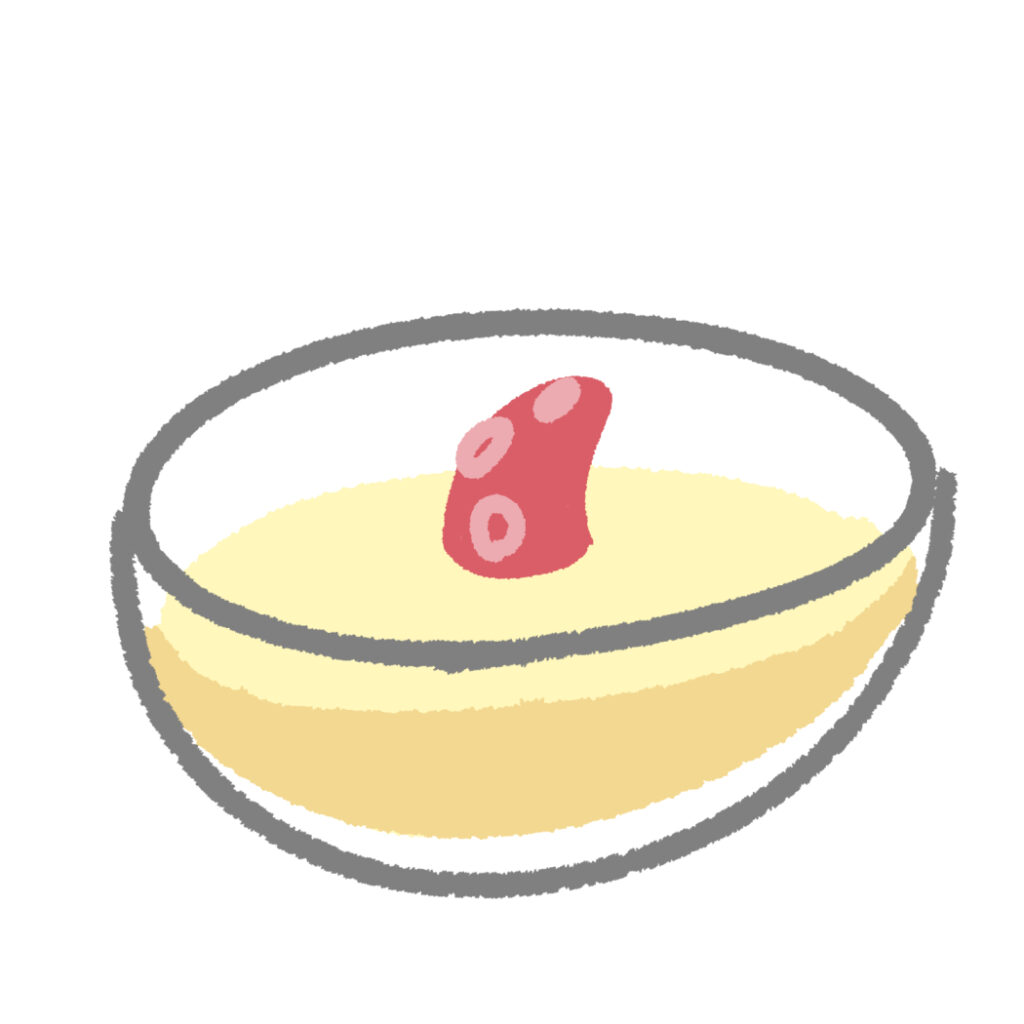
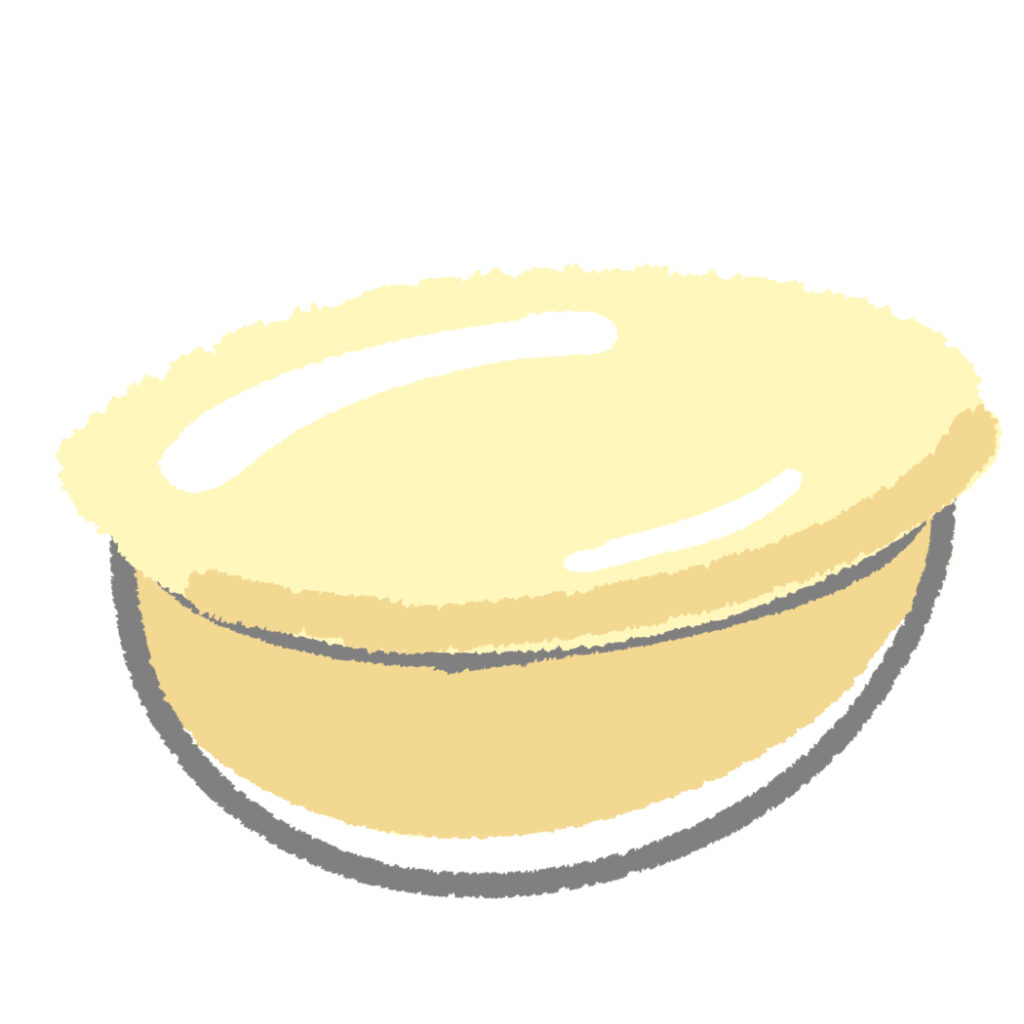
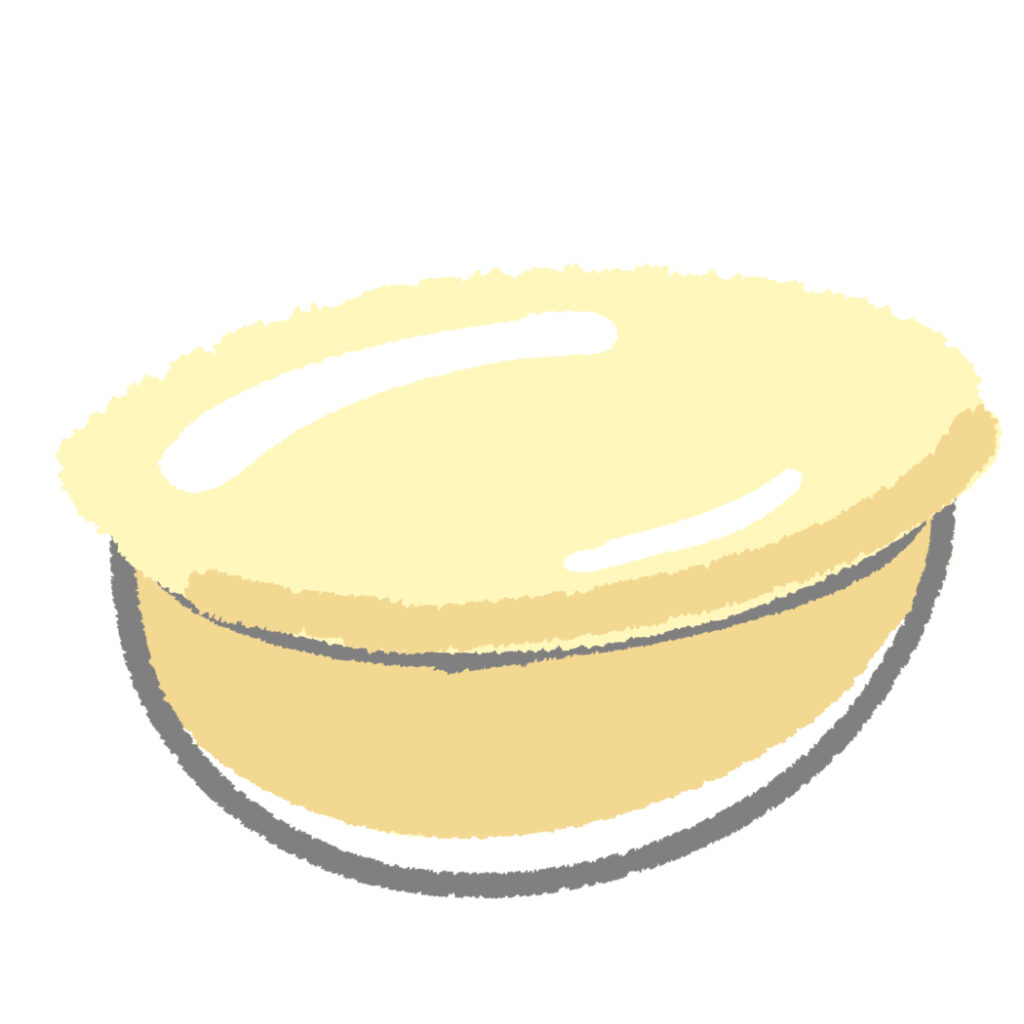
穴ちょうどくらいでも可。この後揚げ焼く工程で膨らむので、気持ち少なめが吉
じん粉を入れている場合は生地が柔らかいので、薄皮ができていることを確認してから回す。
縦に引っ張り上げようとすると崩れやすいので、串で生地を横に回転させながら縦に90°立てる。
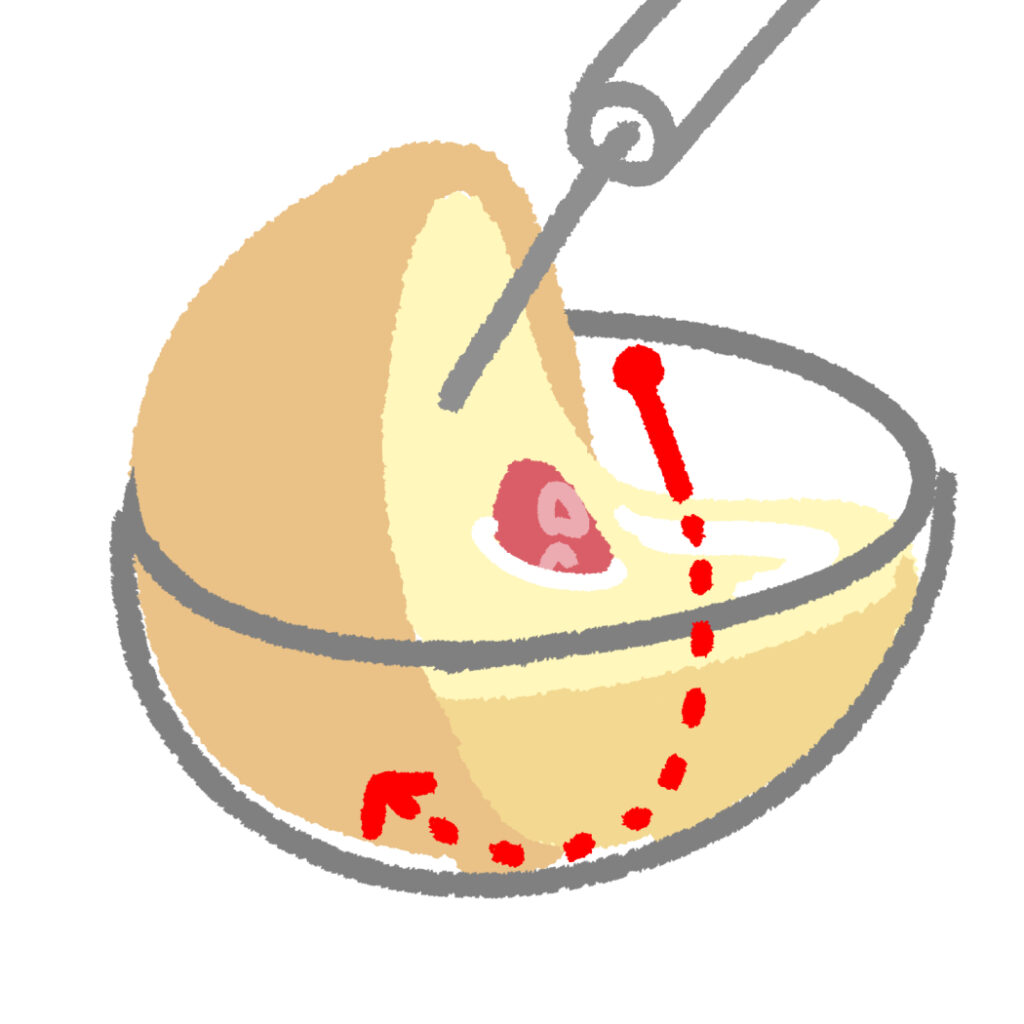
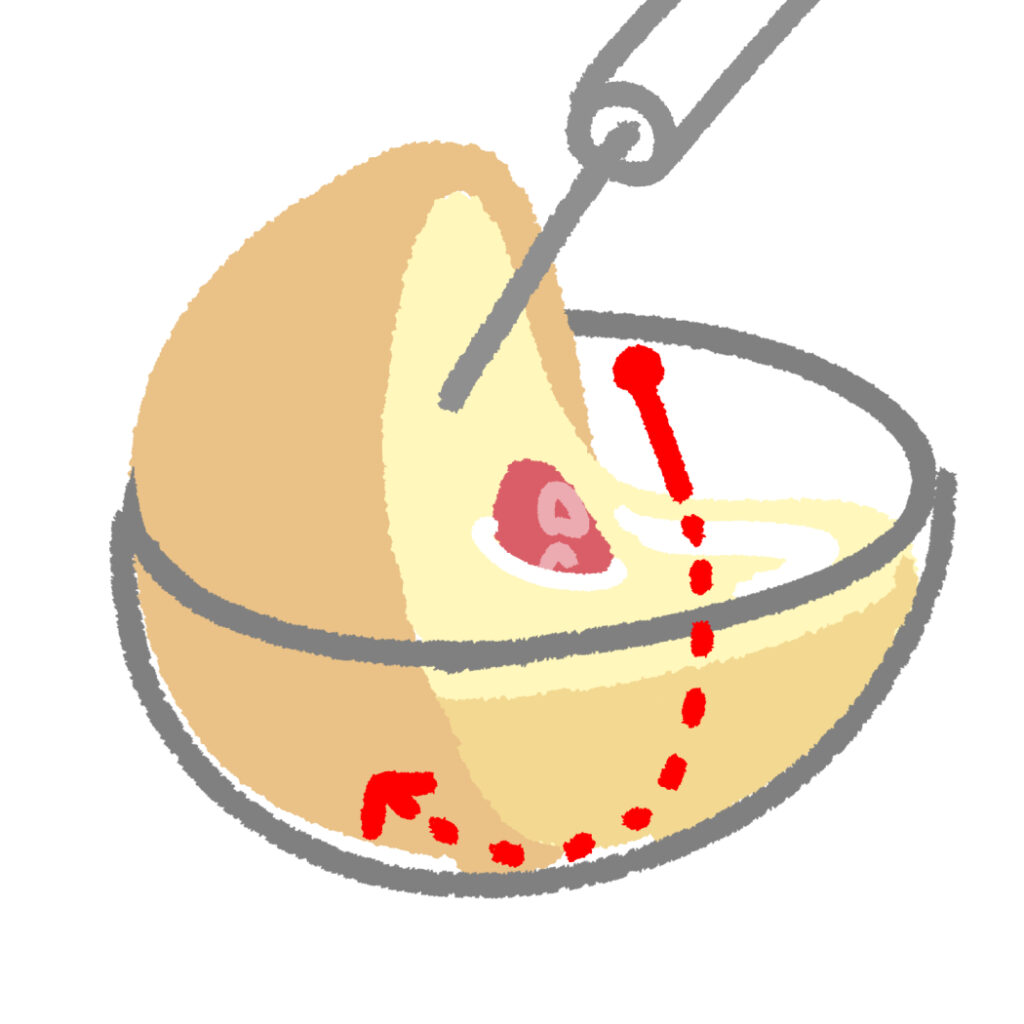
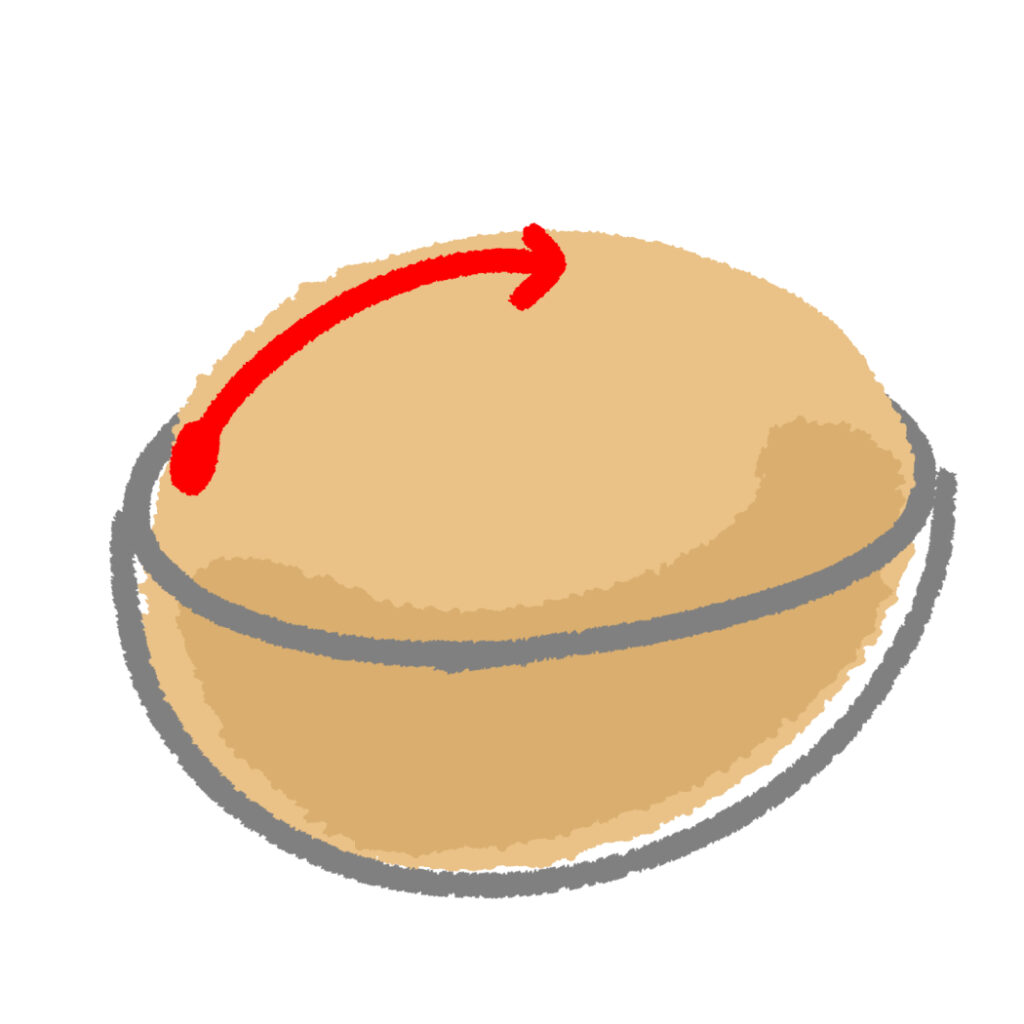
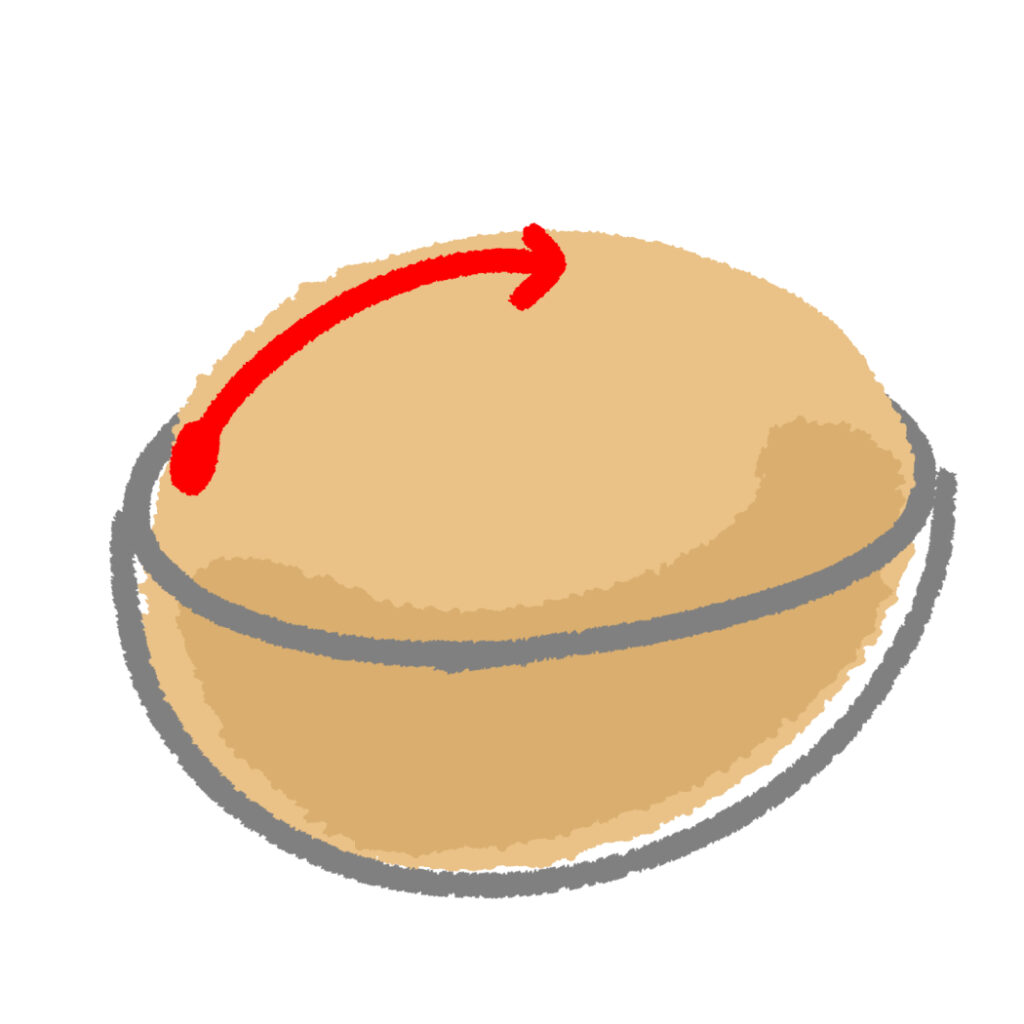
皮の外側から串で刺してさらに90°縦に回す。
サラダ油を回しかけ、揚げ焼いて皮をカリカリにする。背徳感に耐えられるのであればラードを使うのもアリ。
脂を吸って膨らんでくるので、コロコロ転がして満遍なく熱を通し、まんまるに仕上げていく。
表面を串で引っ掻いてガリガリと音がすれば完成!!


・じん粉を入れると生地が柔らかくなるので丁寧に!
・生地は穴から溢れすぎないように!(最後に油を吸って膨らむ)
実食!!





見えますか、ガリガリの外皮が…
なぜかタコを入れ忘れた個体だったんだけど、写りがいいのでご愛嬌。
ぜひお試しあれ…


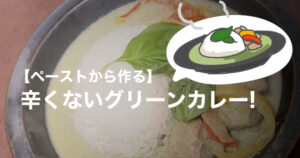







コメント